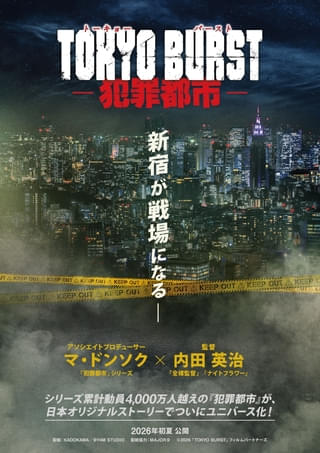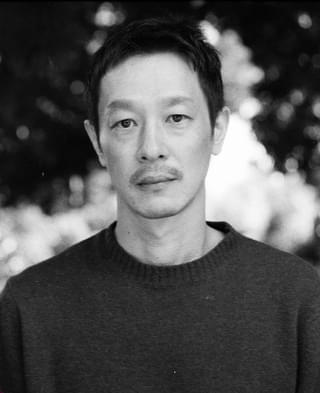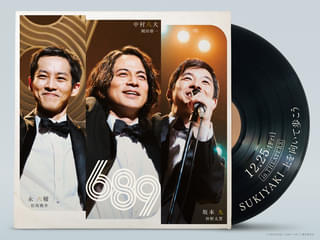コラム:佐々木俊尚 ドキュメンタリーの時代 - 第108回
2023年7月14日更新
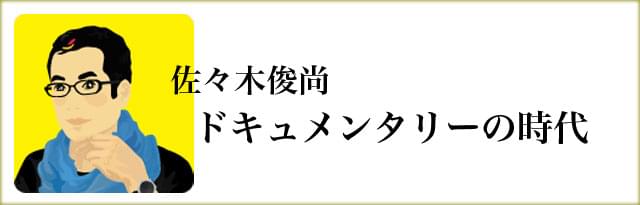
第108回:ウムイ 芸能の村
沖縄・宜野座村で琉球舞踊や三線、獅子舞、島太鼓などさまざまな伝統芸能にかかわっている9人を描く。ナレーションはなく、客観的な解説もなく、登場人物たちの静かな語りのみで物語は進んでいく。そう説明されると淡々とした作品に感じるかもしれないが、実際に本作を鑑賞すると、映像の力が画面のすみずみにまで漲って、ラストまで一気に引きこまれてしまう。実に力強い映画である。

そもそも冒頭に登場する獅子舞がすごい。本土の人間が見慣れている、正月に現れるあの唐草模様の獅子舞とはだいぶ違う。構造は本土のものと同じなのだが、全体の動きがなんともヌメヌメしていて、くわえて南方独自のマジックリアリズム的な趣がある。そんな獅子舞が、沖縄の集落を歩いている。そういう大型獣が本当に棲息しているのじゃないかと思わされるほどだ。
沖縄でもどこでも、伝統芸能は後継者が少なくなって、危機に瀕している。伝統芸能は「保存しなければ」という意志のもとに、保存のための芸能として生き残っていく。あるいは観光地などで、観光の演し物として観光客に見せるために芸能が維持されていくこともある。

しかし本来の伝統芸能は、「保存のため」でも「観光客のため」でもなく、まず「自分たちのため」であったはずだ。自分自身のためであり、自分が所属する共同体のためであり、あくまでも「わたしとわたしたちのための芸能」だったのである。
本作は、おそらくメディアでは「伝統芸能を守る人たち」というような文脈で語られるだろう。しかしわたしは本作を観て、そういうステレオタイプな文脈とはまったく違う印象を持った。本作に登場する老若男女9人の人たちは、「わたしとわたしたちのため」に自分たちの芸能を演じているように強く感じたのである。

彼ら彼女らは、さまざまなところで踊り、演奏する。室内での練習、ホールの舞台、煙が焚かれた夜の野外の舞台、大きなガジュマルの木がそびえる丘。海辺の砂浜で漁師の装束に身を包み、投網をする舞は、古代から続く人々のいとなみをそのまま再現しているように感じた。ひとりが言う。「伝統に触れることは過去の人たちの思いに触れることと同じ」
ただ「伝統を守る」ということだけでなく、自分の身体と心の奥底に共同体のDNAが根を張り、それが芸能というかたちで身体の表に出てきている。そういう感慨を受けたのだ。だからこそ、ナレーションも解説もない本作が、これほど力強く心に刺さってくるのだと思う。
音楽映画が好きな人、沖縄の海と空が好きな人にはぜひお勧めしたい作品である。
----------
■「ウムイ 芸能の村」
2022年/日本
監督:ダニエル・ロペス
7月15日からポレポレ東中野ほか全国順次公開
筆者紹介

佐々木俊尚(ささき・としなお)。1961年兵庫県生まれ。早稲田大学政経学部政治学科中退。毎日新聞社社会部、月刊アスキー編集部を経て、2003年に独立。以降フリージャーナリストとして活動。2011年、著書「電子書籍の衝撃」で大川出版賞を受賞。近著に「Web3とメタバースは人間を自由にするか」(KADOKAWA)など。
Twitter:@sasakitoshinao