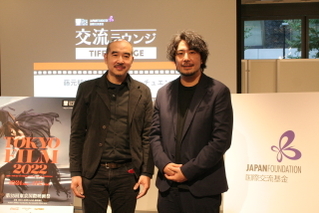ここを逃げたい、どうすればいいですか――「海辺の彼女たち」藤元明緒監督が語る“外国人労働者の現実”
2021年4月30日 09:00

「見た方がいい」という言葉よりも「見るべきだ」という強い思いが引き出される。「海辺の彼女たち」(5月1日公開)とは、そういう映画だ。スクリーンに映し出されるのは、あくまでもフィクション。しかし、そこに映し出された“世界”は非現実的なものではなく、決して他人事でもない。私たちが暮らす日本という国で“彼女たち”は確かに生きている。
第68回サンセバスチャン国際映画祭、第33回東京国際映画祭、第42回カイロ国際映画祭で注目を集めた本作は、東京国際映画祭「アジアの未来部門」グランプリ受賞作「僕の帰る場所」で注目を集めた藤元明緒監督による長編第2作。日本における外国人技能実習生の失踪問題を背景に、より良い生活を求めて来日したベトナム人女性3人が、きらめく未来を夢見ながら、過酷な現実と闘う姿を描いている。
ベトナムからやってきたアン(フィン・トゥエ・アン)、ニュー(クィン・ニュー)、フォン(ホアン・フォン)。彼女たちは日本で技能実習生として3カ月間働いていたが、ある夜、過酷な職場からの脱走を図った。ブローカーを頼りに、辿り着いた場所は雪深い港町。不法就労という状況に怯えながらも、故郷にいる家族のため、幸せな未来のために懸命に働き始める。
「僕の帰る場所」では、在日ミャンマー人の移民問題に目を向けた藤元監督。「海辺の彼女たち」はどう生まれ、スクリーンへと羽ばたくことになったのだろうか。(取材・文/編集部)

(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
――企画の発端となったのは、2016年。SNS上で出会ったミャンマー人技能実習生の女性から“SOSメール”だとお聞きしています。どのような経緯で、そのメールを受けとったのでしょうか?
藤元監督:当時「僕の帰る場所」の編集作業を行っていたのですが、趣味の一環として、ミャンマー人の妻と立ち上げたFacebookページを運営していました。ここではミャンマー人向けのビザ情報、観光情報を発信していたのですが、そのうちたくさんのミャンマーの方々にシェアされるようになったんです。やがてMessengerを通じて、多くの連絡が届くようになりました。彼女からの“SOS”は、そのなかの1通だったんです。
――そこにはどのような事が記されていたのでしょうか?
藤元監督:朝から晩まで働かされ、残業もさせられる。交わした契約とは異なる状況で「ここを逃げたい、どうすればいいですか」という内容でした。逃げてしまえばステータスが悪くなるということを聞いていたので、彼女に「少し待ってください」と伝え、しかるべき機関に連絡をとったんです。彼女の連絡先を教えたんですが……両者のやりとりが上手くいってなかった。(機関は)「助ける」と言いながらも、連絡をとっていなかったようなんです。彼女はその対応に怒ってしまい「誰も何もしてくれないのなら、逃げます」と言い残して、職場から去ってしまった。僕自身は何もできなかった――すごくショックだったことを覚えています。

(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
――「技能実習」というモチーフは、その経験からすくい取ったものだったんですね。では、本作の物語は、どのように紡いでいったのでしょうか。
藤元監督:ストーリーの大枠は、2つの出来事が核となりました。ひとつは、18年の暮れに目にした、技能実習生の苦境をめぐる報道です。一度ならず、何度かニュースになっているのを見ました。ありえないほど不平等な環境に置かれている。彼らがそこまでして、日本に残らなければいけない理由とはなんなのだろうと。

(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
藤元監督:もうひとつは、妻が外国人としての生き辛さを抱えていたというもの。彼女は、僕と出会うまでに、日本で10年間暮らしていました。経験してきた“嫌なこと”を常々聞いていましたし、その日々が積み重なったことで、この映画を撮ろうと思いました。そこから16年の“SOSメール”を思い返し、職場から逃げたミャンマー人技能実習生の“その後”を追いたいと考えるようになったんです。
――本作の冒頭は「職場からの脱出」という光景から始まります。「逃げた後の生活」を描くためには、必然の展開だったわけですね。脚本作りに関しては長期間の取材を行ったようですが、どのような人・場所に話を聞きにいったのでしょうか。
藤元監督:取材は19年からスタートさせて、撮影直前の20年2月まで行っています。主に話を聞かせて頂いたのは、失踪した技能実習生をかくまっているシェルター。「どうやって逃げるのか」「逃げた後のステータスはどうなるのか」「どこでオーバーステイとなるのか」など、失踪した後の枠組みやシステムについてお聞きしました。この点は、フォンたちが“どのように逃げるのか”という動線に反映しています。

(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
――ここまでお話を伺っていると、奥様の存在も大きかったことがわかります。
藤元監督:僕は男ですから、映画の感情面において、女性の意見も知っておくべきだと思ったんです。妻はミャンマー人ですが、日本で感じたことについては、ベトナム人のフォンたちとの隔たりがなかった。家族を養うために、日本に来ているので、もし働けなくなると「お父さんに怒られる」ということも言っていました。加えて、プレッシャーに関しても参考になっています。自分がつまづいてしまえば、働いていない親の迷惑になる。責任感を背負って、日本にやって来ているんです。
――親世代が働いていないという状況は、多く見受けられることなんですか?
藤元監督:いっぱいいらっしゃいますよ。健康上の問題というのもありますが、そもそも居住地に仕事がないという場合があります。例えば、ニューさんの隣の家に住んでいた子は、親に技能実習生として日本へ行かされたんです。本作と同じような雪国で働いていて、その子自身は楽しく過ごしているようです。ニューさんは、その子に「技能実習」についての事を教えてもらい、芝居の参考にしてくれていました。

(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
――本作では「選択」という要素に着目しました。いくつもの決断を自己判断で選んでいるように見えますが、実際は“選ばされている”という印象が強かったんです。
藤元監督:実は、当初は「海辺の彼女たち」ではなく「フォンの選択」というタイトルだったんです。仰る通り、「選択」をしているようでさせられている。この「選択」というのは、彼女たちが自ら見出したものではなく“世界”から降りてきているもの。結局、フェアではないんですよ。それは実際の世界を見ていても感じる部分です。
――なぜ「海辺の彼女たち」に変更したのでしょう?
藤元監督:「フォンの選択」にした場合、「選択」自体にフォーカスが当たりすぎてしまう懸念がありました。「選択」のために、劇中の設定があるという風にはしたくなかったんです。世の中には、フォンたちと同じ世界線で生きている“彼女たち”がいます。タイトルが示すのは、フォンたちなのか、それとも身近にいる“彼女たち”なのか。色々な“彼女たち”を見つめてほしいという意味合いを込め、クランクイン直前に変更を決めたんです。

――では、実際の撮影についてお聞かせください。どのように進行していったのでしょうか。
藤元監督:今回は、ほぼ順撮りです。雪の街で働いてみた3人の“実感”から拾っていくものが多かったように思えます。彼女たちが感じたムードが反映されているんです。オーディションを振り返ってみると、彼女たちそれぞれのバックボーンが、想定している脚本とどれほど近いものなんだろうかということを気にしていました。配役が決まってからも、その点を掘り下げるために、それぞれの話を聞く。それを踏まえて、加筆・修正をする。そういう往復をしていました。
――俳優陣の「人生」を取り込んだということですね。
藤元監督:技能実習生の方々には「自分にはできなかったが、誰かには成し遂げてほしい」という願いを持っている方もいらっしゃるんです。具体的な例を示すと、アンさんの姉は、妹たちのために台湾へ出稼ぎに行っていました。編集の段階でカットしてしまったんですが、アンさんにお姉さんの気持ちを想像してもらい「妹に電話をかける」というシーンも撮影していたんです。「もしかしたら、自分たちもそうなっていたかもしれない」ということを想像して演じてもらう。一種の“パラレルワールド”にいてもらったイメージ。「役名=本名」というのも、その部分での狙いなんですが、最初は嫌な顔をされましたね(笑)。彼女たちにとっては「役者=自分とは異なる人物を演じる」という認識だったので、戸惑いがあったみたいです。

(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films

(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
――撮影監督の岸建太朗さんとは「僕の帰る場所」「白骨街道」に続き、3度目のタッグとなりました。画作りに関しては、どのような取り決めをされましたか?
藤元監督:カメラのポジションについて、かなり注意を払っています。単純に寄る、引くというものではなく「3人の距離感」を守った形での画作りを心掛けていました。最も重要なのは、カメラがどこに置かれているかというもの。全カットとはいきませんが、等間隔を意識しているんです。
――どのような意味合いが込められているのでしょうか。
藤元監督:「観客の皆さんが、フォンたちの“世界”を一緒に体験するにはどうすればいいのか」と考えたんです。カメラのポジションがランダム過ぎてしまうと、彼女たちと行動をともにしている感覚には成り得ません。映画的、もしくは画的な都合も考慮しましたが、基本的にはその精神を守っているつもりです。例えば、3人が電車に乗っている時。カメラは“(4人目として)その場にいる私”となっています。

(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
――注目したのは、フォンがある目的のために、ひとりで街を彷徨うというシーンです。職場、友人、家族から干渉されないという「自由さ」、知らない街を歩くという「不自由さ」が両立している光景でした。
藤元監督:フォンは逃げようと思えば、どこかに逃げられる状況ですよね。僕自身も「逃げてしまえばいいのに」と思いました。でも、それはできない。フォンの願望と、彼女を包み込んでいる世界が、物凄くアンバランスだからです。だからこそ、目的地が決まっているのに彷徨ってしまう。結局、フォンには選択権が与えられていません。「そこに行くしかない」ということになっているんです。

(C)E.x.N K.K.
――2月に起こったミャンマー国軍によるクーデター以降、ミャンマーでは市民への弾圧が続いています。その支援として「僕の帰る場所」のチャリティ上映が企画されました。スタートとして、ポレポレ東中野での上映(4月17日)が行われましたが、反響はいかがでしたでしょうか?
、
藤元監督:まず嬉しかったのは、「映画として面白い」という意見があったこと。映画の鑑賞に加え、支援という形にアクセスできる場を設けてもらったことに感謝しています。そして、映画を見て、現実を知るきっかけになってほしいという言葉をよく使うんですが……では、知った上でどうすればいいのかという具体性。そういうものが都合の良い形で宙ぶらりんになっていると、たまに感じてしまうんです。
――これは悩ましいことではありますが、「実際に行動してみる」というのは難しいことなのかもしれません。
藤元監督:行動してほしいという思いの反面、よほど関心がなければ、ハードルの高い事ではあると思います。
――例えば、作品を見た人に「何をすればいいですか?」と聞かれたら、どう答えますか?
藤元監督:簡単にできる事はあるんですよ。例えば、クラウドファンディングにお金を投じる。そう聞かれた場合は、まずはリンクを共有しています。そもそも支援の“箱”を知らないというケースも多いんです。例えば、署名でもいいと思います。署名の効果を疑問視する意見もあるとは思いますが、意思を表明するということは、その人自身の行動が変わったという事ですから。

(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
――最後に、今後の展望についてもお聞かせください。
藤元監督:現在は、国内配給しかできていない状況です。常々、世界の人々に見てもらいたいと思っているのに、それができていません。海外映画祭での上映は実現させていますが、各国でのシネコン、ミニシアターでの一般公開を行う。これが最大の目標です。稼ぎたいという思いが先行しているわけではなく、自分たちが作った物語が、どのように受け入れられるのかに興味があるんです。「海辺の彼女たち」については、渡邉一孝さん(プロデューサー)と、ベトナム側のプロデューサーがやり取りをしてくれていて、現地での公開を模索しています。これが実現すれば、共同製作で作った意味合いが出てきますよね。互いの国で作品を共有する。まず、やらなければいけないことだと思っています。
(C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films
 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 この世界の片隅に
この世界の片隅に ダンケルク
ダンケルク 1917 命をかけた伝令
1917 命をかけた伝令 アリー/ スター誕生
アリー/ スター誕生 君の膵臓をたべたい
君の膵臓をたべたい ショーシャンクの空に
ショーシャンクの空に
![USB[DVD]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/nowprinting_dvd.gif)
![鈴木さん[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51xoHYM5R2L._SL160_.jpg)