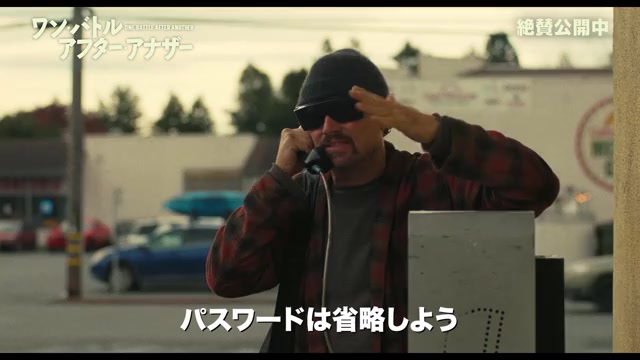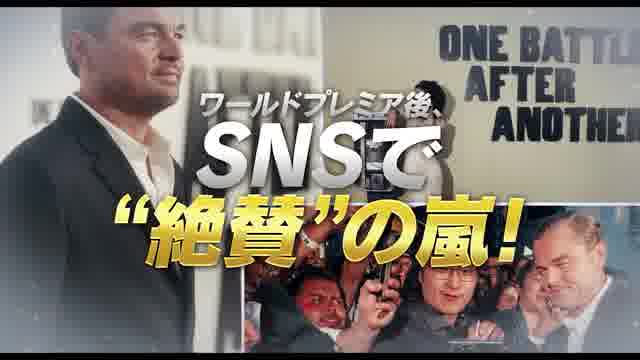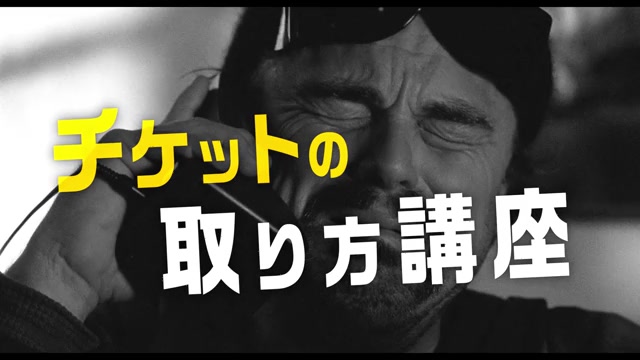「正直よくわかんなかったけど、ショーン・ペンはよかった」ワン・バトル・アフター・アナザー モアイさんの映画レビュー(感想・評価)
正直よくわかんなかったけど、ショーン・ペンはよかった
私の反省は口ばかりのため、結局「また来週でいいか…」を繰り返し、その結果ちょっと気になっていても結局観に行かないまま上映が終了してしまった作品が数本という体たらくなこの2ヶ月間。本作も危うくそうなりかけたのですが一念発起し、最寄りの映画館での上映最終日の最終回、ド平日の21:35~スタートにギリギリ駆け込んでの鑑賞となりました。そしてこの日は仕事の関係でいつもより朝が早かったので、眠気対策のために「眠眠打破」よりさらに不味い「強強打破」を煽り、いつもより気合を入れて本作に臨んだのです。
目にする度にどんどんジャック・ニコルソンに寄っていくレオナルド・ディカプリオですが、実際に動いているのを見ると「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」(02年)の頃から何ら変わらない、あのどんな悪さをしても悪態をついても憎み切れない愛嬌は健在でした。
そしてショーン・ペン。覚えやすい名前と顔立ちで印象に残りやすい割に、その出演作に印象深いものは個人的にはあまりないのですが、しばらく見ない間にえらい老けてて軽くショックです。これは「ユニバーサル・ソルジャー2」(99年)を当時劇場で鑑賞した際にジャン=クロード・ヴァン・ダムのもみあげに白髪が混じっているのを見た時のショックに近い物がありました(いま改めて見ると光の加減で白髪に見えていただけの気もしますが…)と、それはともかく本作でのショーン・ペンの怪演。色欲に溺れ、職務柄の能力が高い故により質の悪い粘着気質を見せるその姿に爆笑です。ショーン・ペンに対してはどことなくスカした風で常に格好つけているような鼻持ちならない印象を抱いていたものですから、こんなアホで格好悪い役を全力で演じている姿にとても好感を抱きましたし、そのインパクトは本作においてディカプリオを凌いでいました。私はこれまでのショーン・ペンの演技を把握している訳ではないのですが、本作においてもディカプリオはその魅力を十分に発揮していたと思うのです。ですがその魅力はディカプリオがこれまでの出演作でも魅せてきたものですので、従来とは違った一面を魅せてきたショーン・ペンの方が、私にとってはより印象に残ったのです。
そんな従来通りの魅力満載のディカプリオに頭は排外主義だけど下半身は博愛主義なショーン・ペン。その他にも魅力的なキャラクターが続々と登場し、それを演じる役者の魅力を十二分に引き出している本作…………だが私は眠った。しかも評判のいいクライマックスのカーチェイスで眠った。気付いたら娘が車道の横に突っ伏して追跡者に銃を向けている。車道にはクラッシュしたとわかる車が2台…。どうしてこのような状況になったのかがてんでわからない。これは痛恨である。ウトウトがはじまった頃、ショーン・ペンが雇った有色人種なのが残念な仕事人(クリスマスの会評)が変な武装集団に娘を引き渡した後、踵を返してその武装集団を襲撃した理由もわからないのですが、しかし私にとってこの映画はそもそもよくわからなかったのです。
物語の軸になっているのは父子の絆の物語なのであろう。育ての父であるディカプリオと血縁上の父のショーン・ペンとが娘を巡って争奪戦を繰り広げているのです。ようやく娘に辿りついたディカプリオに娘が言い放つセリフはその構図だけで胸に迫るものがあるのですが、その後に2つ、3つのセリフで父子のハグにつながるのが疑問です。ディカプリオが娘を愛しているのは明白です。それはよくわかります。子供が生まれるとわかるや否や革命ごっこなんかやっている場合じゃないという意識の切り替えの早さは娘の母親が出産後も子供のためにという意識になれなかった事と対比されて明確です。しかし娘の方はどうなのだろうか?娘からしたら人里離れたアバラ小屋での不自由な貧乏暮らしで今時スマフォも持たせてくれない。その代わり変な装置を常に携帯させられて、空手教室には通わせてくれるが、これも娘がやりたがって通いはじめたのかはわからない。世の子供の習い事の大半が親の意思で通わせはじめる様に護身用として最初は無理矢理に通わせはじめただけかもしれない。そして娘の交流関係が広がるのを嫌がり、娘の友達さえも邪険にし、常に葉っぱで軽くラリっているような父親が迎えに来たところで、構えた銃の引き金を引くだけなのでは?…というのはまぁ冗談にしても、父と離れ離れになった娘が父を恋しがっていた印象が全くなく、気に掛けるのは自分の母がどんな人だったのか?という事だけという感じだったので、この父子が無事にハグできた心境がよくわからないのである。
そして今回のディカプリオは元テロリストの爆弾魔である訳ですが、別にテロリズムが肯定的に描かれているわけではないのです。テロ集団のリーダーである娘の母親(ディカプリオの恋人)が『排外主義者、資本家、中絶反対論者どもなんか〇ソ喰らえ』みたいな事をのたまい暴れまわる冒頭ですが、そんなご立派な大義を掲げる割には押し入った銀行の黒人警備員を些細な事で、でも偶発的にではなく明確な意思を持って銃殺し、警察に取り押さえられると、いとも簡単に仲間の居所をゲロるのです。子供の事でディカプリオと言い合いになるシーンで映る彼女の実家らしき家の立派さを見るに結構裕福な家庭の出身のようですが、中絶反対論者の施設だかに爆弾を仕掛け、犯行予告の電話までしているのですから彼女の思想的には子供をおろすのも全然アリなのだと思うのです。しかし子供が出来たら自分たちの活動がどうなるのかなんて1ミリも考えていない様子で、お腹に子供を宿しても仲間とハイになってマシンガンを乱射する姿が描かれます。そうして生むだけ生んだ後で子供より私を見てほしいとかいうモノローグが入るあたり、彼女ののたまう大義に対する信念がいかに薄っぺらいかがよくわかる作りなのです。そしてそれはディカプリオの役にしてもそうです。彼が爆弾を作って彼女の活動に協力するのも単純に意中の女性と一緒にいて、彼女の気を惹くことだけが目的だったのです。なので子供が出来たと知るや否やテロ活動(大義)からなんてさっさと足を洗って子供のために暮らそうと言い出すのです。さらに彼は一応排外主義に反旗を翻して活動していたわけですが、娘の友達に対しては「怪物ども」と吐き捨て、排他的な態度を見せます。まぁ肌の色の問題と学校でなんとなく浮いてそうなグループという問題は別物なので、もしかしたら矛盾はないのかも知れませんが、どちらにしろ私にはこれらの描写を見るに「先進国に生まれたくせにご立派な大義を掲げて暴力革命だとか言ってる連中なんてこんなもんだよ」という監督の皮肉にしか見えなかったのです。しかしそれならばこの映画のオチで娘が嬉々としてテロ活動に出かけ、ディカプリオもそれを微笑んで見送るというラストは一体何なのか?母親は甘ったれのお嬢さんが承認欲求と破壊衝動を満たすために活動してただけだけど、娘は貧乏暮らしで純粋に活動している“立派”なテロリストっていう事なのでしょうか?
そして一方で彼らと対峙する白人至上主義者たちも「未だに白人至上主義なんて信奉できるおめでたい奴らなんてこんなもんだよ」といわんばかりにステレオタイプ的な滑稽さに溢れています。こういう物語に登場する思想信条や各種組織のいずれにも肩入れせずに俯瞰して見せていくという表現があるのはわかるのですが、それを俯瞰して見せられてこちらは何を汲み取ればいいのかはいまいち私にはわかりませんでした。それに“俯瞰”と言ってもディカプリオが可愛すぎなので、どうしてもディカプリオに視線を合わせようとしてしまうのですが、しかしディカプリオ自身が自分の過去のテロ活動をどう思っているのかがよくわからないのです。16年間娘に不自由を強いながら人目を忍ぶような生活をし、いつ自分たちの正体がバレるのかヒヤヒヤしながら常に葉っぱでラリっているのも自分の過去の活動に起因するのですが、そこら辺への心情がよくわかりません。ただ先に記したように娘が活動をはじめた事に対して反対の様子もないので、あまり過去については後悔はないのかな?と、結局ディカプリオにも肩入れしきれないまま、この映画の何を見て楽しめばいいのかよくわからなかったのです……まぁ眠ったんですけどね!
特に何を言わんとする作品でなくても“ありのまま”を表現されると何故か感動するという感覚があります。ですのでもしかしたら現在のアメリカという国に漂う雰囲気を理解している人から見るとこの作品は「そうそう、これこれ」という感動に溢れているのかもしれません。しかし残念ながら私には今のアメリカに対する理解はいくつかの創作物と報道の切れ端から垣間見た程度のものですので、その手の楽しみ方も見出せませんでした。まぁ一つそれらしい事といえば、女性は命がけで子供を出産するのだから生めば“母親”になれるけど男は一生懸命子供に尽くさないと“父親”とは認めてもらえないよ!って事だったのかもしれませんね!「男はつらいよ」なんて時代錯誤なフレーズが頭をよぎり、それにしても強強打破は不味かったのに効かなかったなぁ~と苦い思いで鑑賞終了です。
こんばんは。
コメントありがとうございます♪
「眠眠打破」は知ってるけど
「強強打破」もあるんですね!
それでも効かなかったモアイさんが強い。。w
カーチェイスウトウトとは〜!
凄い画でしたよ。
酔いそうでした。
〉下半身は博愛主義なショーンペン
↑爆笑ww
ショーンペンはインパクトありましたね!
評価は違いましたがモアイさんのレビューに書かれている事は共感です。
私はそこまで真剣に考えておらず頭空っぽなので純粋に楽しめました♪
モアイさん、ご丁寧にありがとうございます。ショーン・ペン巡り(勝手に)第一段は終了してかなり満足しました。第二段はいつになるかまだ決めてませんが、自分の責任と気持ちで見ますので大丈夫です~
この映画でショーン・ペン?!と思い、昔の彼が出る映画を配信で何本か見ました。演技が上手い、どんな役も素晴らしくこなすすごい役者だと初めて知りました!
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。