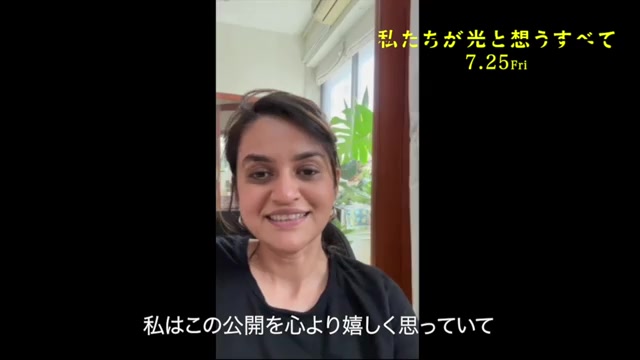「言語化できない強い余韻──インドと日本の現在をつなぐ映画」私たちが光と想うすべて nontaさんの映画レビュー(感想・評価)
言語化できない強い余韻──インドと日本の現在をつなぐ映画
言葉にして感想を書いてしまうと、何か大事なものが抜け落ちてしまうような、言語化できない強い余韻を残す映画だった。
いつまでもそれがなんなのか考えてしまいそうだから、とりあえず鑑賞直後の感想を書いてみたい。
インドの映画はこれまで何本も観ているけど、エンターテイメントの極致のような映画ばかり。本作は、そうしたエンタメ性は全くない。
ただ、この映画を観てはじめて、僕らと同じく、現代を生きる困難や葛藤を抱えて一生懸命生きている個人、国籍は違えど同じ悩みを持つ同志として話してみたくなる個人としてのインドの人の姿を教えてもらった感じがした。
映画の冒頭で、正確な言葉は覚えてないが「この町で暮らして10数年以上になる。でもこの街を故郷と呼ぶには躊躇してしまう。いつお前はここからででいけ、と言われるかわからないから」
こんなようなモノローグが街の風景をバックに流れる。
これは、自分が安心して所属していると思える場所などないんだという本作の1つのテーマの提示ではないかと思った。
そしてその後のストーリーで、凄まじい発展の最中の現代のインド社会の様子が丁寧に描かれていく。
僕はインドに行ったことがない。敬愛する藤原新也の「インド放浪」(彼が20代、1970年代に出版された凄本)の近代以前の価値観が色濃く残る時代のイメージでインドを捉えがちな僕の認識もひっくり返してくれた。
今のインドは、日本で言えば、明治の近代化、戦後の民主化と自由主義と経済発展、さらに男女雇用機会均等法とグローバル化の影響が同時に訪れているような状況なんだと思う。
基本的にはポジティブな発展ではあるけれど、そこで起きている共同体の喪失や個人が機能として能力で測られること。自分らしさを自分で見つけてそれにしたがって一人一人が自分で人生を切り開かなければいけない……そうした困難が丁寧に描かれた映画だと感じた。
しかし、そうした時代の中でも、資本の論理で人を機能としてみるような流れに飲み込まれず、本来の人間らしい関わりを大事にしている。そんな人としての強さも強く感じさせられた。
ここらかは余談になるけれど、先日、永田町にある自分の会社の近所のコンビニでそんな体験があった。
飲み物と電子タバコを買ったら、レジの外国人の若い女性(おそらくインド出身)が「マスカットがお好きなんですね」と話しかけてくれたのだ。
? 何を言われたのか一瞬わからなかった。そして手元の商品を見て気付いた。僕の買った電子タバコがマスカットフレーバーで、飲み物がマスカット味のいろはすだったのだ。
なんかすごく嬉しかった。それに何か大事なことを教えてもらったと思った。
店員と客で、コンビニは資本主義な等価交換の場。忙しい店だから効率が大事。そこに個人的な、相手のその人らしさを見て、それを承認するというようなことは、なかなかできることではないと思う。
だいたい僕らは会社員として、有能で成果を出しているか、組織に与えられた役割と責任を果たしているか……そんな画一的評価の中で生きているから、自分が他の人とは違う個性のある人であるという自己重要感が得られなくなっている。それが現代の発展の裏にある大問題であると思う。(庵野秀明のエヴァは、そうした彼の個人的欠落感を、キャラクターたちに反映させて、そこからの救済の可能性を探る作品でもあると思う)。
そうした僕ら日本人の現代の課題にも通じる普遍性を持った素晴らしい映画。満席だったから、すでにその評判は周知されているのだろうけれど。
さらに余談。
こんな感想を映画を観たあと小伝馬町のインド料理店「デシ タンドール バーベキュー」で、ビリヤニ付きのちょっと贅沢なランチを食べながら書き始めていた。
ビリヤニが素晴らしく美味しかった。会計の時にそんな話を店員さんにした。僕はチャーハンみたいなものだと思ってたけど、大間違い。2〜3時間も手間のかかる炊き込みご飯のようなものなのだとか。冷凍のお店も多いけど、味が落ちるから、彼の店ではやらない。人気でもたくさん出せないのだそうだ。
彼の仕事にかける意気込みと倫理観、誇りに触れて感激。握手して店を後にした。
映画の感想からずいぶん離れてしまったけど、直接その素晴らしさを語れない、でも何かが強く心に残る、そんな映画でした。